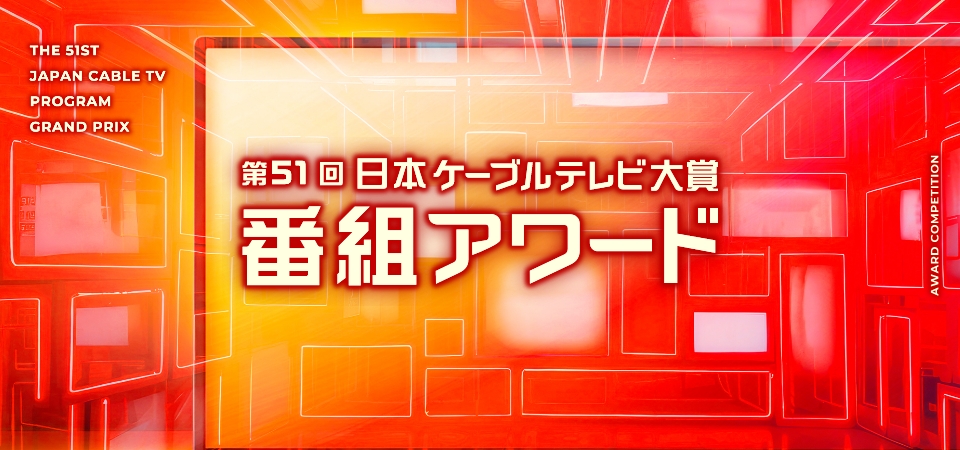
審査員長 音 好宏 氏
第51回日本ケーブルテレビ大賞番組アワードで受賞された皆さま、誠におめでとうございます。
昨年50回の節目を迎え、新たに部門等を整理するということになった今回でございますが、正直申し上げまして、審査は大変難しいものでした。
現在のケーブルテレビが置かれている状況が番組に反映されている作品が大変多くございました。社会のインフラとして地域を支えるということを行いながら、もう片方で放送サービスとして地域の諸課題を見つめ、そして、それを番組化していくという作業があり、その作業の結実として、番組アワードにエントリーされたものと認識しております。
昨年を超える212本という多くの応募があったことに、作り手の現場の心意気というものが表れていることを感じました。また、エントリーされている作品は、ジャンルが非常に幅広くなったように思います。例えば、地域社会の歴史的な問題を俯瞰して見て行くとか、映像記録としてアーカイブして残して行くなど、これはケーブルテレビにしかできないことだと思います。そのほか、このところ様々な災害が多発をしておりますけれども、災害に地域の目線で向き合って行く。言うなれば、災害に向き合い、なおかつ防災に向けた活動、それらが作品になっているものもございました。
今回、審査会において議論した結果、これまでに無かった二つの特別賞を設けて贈賞しました。ひとつは「ソリューションジャーナリズム賞」。地域が抱える課題の解決に向けて、番組を通じて努力を重ねている作品を高く評価いたしました。
もうひとつは「地域未来デザイン賞」。この賞も最後まで審査会で議論したのですが、言うなれば地域の未来を創る番組だということで決定いたしました。各地では、過疎化、少子高齢化などさまざまな問題を抱えていますが、そこを乗り越えて地域をデザインして行こうとするきっかけをケーブルテレビが担っています。
実は中海テレビ放送の故・秦野一憲様にご教示いただいたことなのですが、地域社会にとって社会的責任というものをケーブルテレビは持っているということ。その地域に対する社会的責任が番組に反映されて行く、もっと申し上げれば、地域社会に対する恩返しとして、あるいは地域社会で一緒につくり上げた作品が、番組アワードでこのように顕彰されることは非常に素晴らしく、大切なことだと思います。
応募作品212本には、本当にさまざまな素晴らしい作品がございましたが、本日発表しました作品に賞を差し上げることにいたしました。来年もまた、より一層多くの作品がエントリーされることを期待しております。
(2025年7月24日贈賞式 審査員総評より)
グランプリ 総務大臣賞
株式会社ジェイコムウエスト 神戸芦屋局
かわるもの、かわらないもの
~神戸今昔~
受賞者の声

中西 翔 さん
審査員長 音 好宏 氏
阪神淡路大震災から30年目を迎えた今年、震災により被害を受けた地域の姿と、その後の地域の変貌を丁寧に振り返る地元のケーブルテレビならではの作品。地域にとって映像の資料的な価値が高いことはもちろん、大規模自然災害が多発する昨今、このエリアの住民の実体験に基づく証言の数々は、私たちの防災観・防災意識に示唆に富むところが少なくない。
審査員 橋本佳子 氏
阪神淡路大震災から30年。本作は、震災当時の写真と現在の街並みが重ねられるというシンプルな構成ながら、災害の甚大さとそこからの復興の歩み、そしてさらに変貌しようとする街を、深く感じ取ることができる。30年が経ち「当たり前の生活」を取り戻した地域の人々のインタビューは、表情も含め どれもが心に残る。番組のベースとなる写真の多くは昨年末に閉館した神戸アーカイブ写真館のものだ。時代を記録し保存していくことは未来へ向けての行為に他ならないことを改めて静かに伝えた。
審査員 藤森 研 氏
30年前、ボランティアで行った神戸の街は、建物がばらばらの角度で傾いていて、平衡感覚に変調をきたしたのを覚えている。あれから、街は変わった。
その変遷を写真で記録したことも貴重だが、災害時に有益だったことを改めて住民の証言で残した点でも有意義だ。
ある地区は区画整理をして、今はせせらぎが流れる。ある商店街では井戸水が、大いに皆の助けになったという。当時の「お互いの思いやりの心」を語る人もいた。
30年の節目に、人間の営み、時代の変貌を考えさせてくれる作品だ。
審査員 日笠昭彦 氏
写真の定点観測(同ポジ検証)という手法はそれほど珍しいものではありませんが、生田神社の当時の宮司やパン屋、宝飾店、喫茶店、東さんの話など30年を振り返る言葉はどれも深みがあって芯が太い。場所の選定や人選の妙は(東さんの力もあったかもしれませんが)長く地元を見つめるケーブルテレビならではです。そして、その言葉を視聴者に立体的に浮かび上がらせたのは当時の写真。あらためて映像・画像の持つ力を感じました。30年経って人によっては不鮮明な残像になりがちな体験を、映像と証言で見事によみがえらせました。編集や言葉の選択も的確で、オープニングやエンディングも「こう見て」という押しつけが無く心地よかったです。
審査員 服部洋之 氏
写真は様々な記憶を呼び起こす。会話の中身、お天気、体調、思い出をその瞬間に閉じ込める。震災直後と復興した現在の町の姿を定点観測することで、阪神淡路大震災から30年の間を垣間見る。しかし町は復興したものの、当時の写真を目の当たりにして、人々はつい昨日の出来事のように語る。番組のカメラもその表情と気持ちを丁寧に、しかし客観的に捉える。「記録する」ことの意義がジャーナリズムにはある事を再認識する番組だ。
審査員 金森郁東 氏
本作がこの賞を受賞するのは異存なく賞賛に値します。本当におめでとうございます。
内容の秀逸さは他の審査員も書かれているので譲りますが震災から30年と言う節目で過去ライブラリをアーカイブとして残して活用して保存する大切さを再認識させて頂きました。能登半島地震は私の地元であり当事者であるだけに伝えて行きたい事と、痛感しました。
本作がドキュメンタリー部門への応募ですが審査するなかでコミュニティ部門との差別化考え、ドキュメンタリーと言う言葉に身構えてしまいます。
準グランプリ
株式会社倉敷ケーブルテレビ
真備町写真洗浄
5年半の活動に節目
受賞者の声

岡村 祐紀 さん
審査員長 音 好宏 氏
2018年の西日本豪雨により、甚大な被害を受けた倉敷・真備町で行われてきた被災した写真の洗浄ボランティアの活動が、その役割を終えることを機に、これまでの活動を振り返る。豪雨による災害という地域の「負の記憶」と、それに向きあい続けてきた人々の想いに、地元のケーブルテレビが寄り添い続けてきたことがわかる作品として、その活動も含め評価したい。
審査員 橋本佳子 氏
被災した写真の洗浄をおこなう団体の災害直後の活動の始まりから役割を終えて閉所するまでの5年半を、良くぞ映像の記録として残してくれたという思いを抱いた。「与えて与えられる」ボランティアの核心を突く言葉が響く。この小さな活動が同じ被災地の能登へそして他府県へ技術が伝わっていく様子は感動的である。20分足らずの尺ではあるが、ボランティア精神とはなにか、その真髄が凝縮された作品にまとめあげた。ボランティアという言葉がこの国に根付いてからおよそ30年。その現在地を余すところなく伝えた佳作。
審査員 藤森 研 氏
水害大国日本で、こういう一見小さな助けでも人の心に静かに寄りそうボランティア活動が育っていることに、教えられる。
圧倒的な人々は汚れた写真を処分してしまうが、復元は、かなり可能なのだ。「処分してしまう前に写真洗浄を知ってほしい」という簡明な呼びかけが、この作品の命だ。短時間の番組だが、一点に絞りストレートに伝えようとする姿勢に好感が持てた。
西日本豪雨水害で「あらいぐま岡山」が始めた写真洗浄の活動は能登半島地震の被災地にも広がった。さらに各地に広がるよう、応援したくなってくる。
審査員 日笠昭彦 氏
自然災害を前に人間社会の無力さを実感する昨今。奪われた一人ひとりの尊厳に心を砕く活動の記録です。5年半で12400人のボランティアが517000枚の写真を洗浄」とはとんでもない功績です。「思い出は買い戻せない」という言葉通り、だからこそ泥土にまみれた写真を救うことで災害によって損なわれた被災者一人ひとりの人生を修復している気がします。そんな尊いボランティア活動を丹念に描写した記録ですが、長期取材だからこそ見えてきた様々な事象を地元メディアとしてきちっと描いていました。その後の全国への広がりに関する取材も良かったです。
審査員 服部洋之 氏
災害支援の方法はさまざまだ。被災地で直接活動するボランティアもあれば、募金などの後方支援もある。災害において優先されるのは、支援する側でなく、被災者であることは自明の理だが、時に価値観が錯綜する。番組は、現地において精神的な後方支援を行う「写真洗浄」を長年追いかけた最終回だ。思い出の写真は人々の心を解きほぐす。活動を長期間記録しつづけた番組の功績を、他地域へ横展開できることを願う。
審査員 金森郁東 氏
写真洗浄の数51万枚と聞くと驚愕です。
被災した方々は日々生きることで精いっぱいです。優先順位が平時と異なります。人の記憶は断片的に薄れていきます。
写真やその他思い出は何とか残したいと思うのは私も能登半島地震以来痛感しております。私も、細かなところでボランティアの方々の力に助けられました。
それを5年間、こまめに追いかけて頂いた地元に根差したスタッフの取り組みに感激しております。この制作体制を今後とも維持されることを望みます。
ソリューションジャーナリズム賞
株式会社広域高速ネット二九六
NEXTEP
~地域から…未来への提言~
砂浜が消える…
九十九里浜で進む海岸侵食
受賞者の声

萩谷 智弘 さん
審査員長 音 好宏 氏
メディアが半身乗り出して、地域社会の課題解決に地域住民とともに取り組むジャーナリズム活動のあり方を「ソリューション・ジャーナリズム」と呼ぶが、本作品で示された砂浜の浸食・後退という地域で起こっている問題を息長く追いかけ、その課題解決に向けた地域の合意形成に寄与しようとする広域高速ネット二九六の取り組みは、まさにソリューション・ジャーナリズムと言えよう。地域社会に対する姿勢を含め、高く評価したい。
審査員 橋本佳子 氏
メディアが単なる報道を超えて自ら地域の課題解決に取り組むという今後の地域メディアのあるべき姿の一つとして創設された「ソリューションジャーナリズム賞」。その第1回の受賞にふさわしいシリーズだった。一昨年グランプリに輝いた「高齢ドライバーの事故を減らすには」に引き続き、今回も多角的な取材と検証に基づき、海岸侵食をテーマに据えた提言は具体的で説得力がある。何よりも「自分ごと」として九十九里浜を守るために何ができるかを取材し続け14回にわたるシリーズを構築したその熱量は驚くべきものだ。いまのテレビメディアに新たな可能性を提示したことに敬意を表したい。
審査員 藤森 研 氏
あの九十九里浜で海水浴場が半減した、という事実にまず驚くが、思えば神奈川に住む私の地元の海岸でも、同じことが起こりかねない。
島国日本の普遍的なこの課題に正面から向き合い、海岸侵食の諸原因の解明、離岸堤や養浜などの対策、時には利害が対立する関係者間の合意形成への多様な試みと、論理的に「解決」へ真っ直ぐに進む作品の流れが快い。
遠州灘、鹿島灘、宮崎海岸なども視野に入れ、緻密な調査で「提言」にまとめる姿勢はこの番組の真骨頂だ。次なるテーマへ取り組みも期待している。
審査員 日笠昭彦 氏
九十九里浜や海水浴場、別荘地としての歴史が興味深く、一見難しそうな「海岸浸食」に対してスムーズな導入。やがて問題を解き進めるにつれて、日常生活で砂浜の役割など考えたことが無かった自分を恥じることになります。放置してはいけない深刻な問題だと認識しました。ヘッドランドや離岸堤など聞き慣れない言葉もわかりやすく解説。中でも「匝瑳の(魅力ある)海岸づくり会議~街頭調査~市長への提言」の流れが素晴らしい。調査報道には緻密さとしつこさが必要ですが、宮崎の取材を含め足で稼いだ検証が見事です。*他局の皆さんも、この海岸浸食や一昨年の高齢ドライバーのような「課題解決型」の企画にぜひ取り組んで欲しいと思います。
審査員 服部洋之 氏
取材力と記述力が「ぶ厚い」番組である。そして何よりも「提言」することが大きな実績といえる。いわば番組のスタジオが「熟議」の場となり、民主主義を具現化していると感じる。様々な利害関係、公共団体の論理、自然現象の複雑性、個々の住民の想い。相反する意見や水面下の思惑などをまな板に載せて、一つひとつ検証してゆくさまは、課題から目を逸らさずに向きあう地域メディアの真の姿を垣間見た。継続は力となるのだ。
審査員 金森郁東 氏
取り常連局の作品で安心して拝見しました。見事にシリーズをまとめて頂きました。
審査員の意見も相違なく何とか上位入選にしたいと思う生みの苦しみでこの賞の名前が決まるまで多くの時間を要しました。
4K制作との事なので私の立場から言わせて頂くといつの間にか4Kが当たり前になっています。4Kのメリットは解像度だけではありません。その有り余る情報量です。そのあたりを考慮頂ければ飛躍的に変わります。今後の番組制作に期待します。
地域未来デザイン賞
株式会社大垣ケーブルテレビ
海津小学校開校記念特別番組
~若き力がつなぐ伝統~
受賞者の声

髙橋 杏輔 さん
審査員長 音 好宏 氏
少子高齢化が日本社会の喫緊の課題であるなか、地元の5つの小学校の閉校と、それらの小学校を統合する形で開校した海津小学校のスタートにフォーカスして、地域の文化拠点、巣立ちの場である学校の姿を未来志向に問うている。閉校した5校の伝統を受け継ぎつつ、地元出身のシンガーソングライターが校歌を作り、校章制作を地元高校生から手がけるなど、若い力による学校作りの姿が清々しい。
審査員 橋本佳子 氏
少しずつ社会が衰退に向かうことを感じることが多いこの数年。日本各地で、あいつぐ学校の統廃合のなか、番組は閉校ではなく開校へのプロセスに焦点をあて、未来への光を描いた。若い力が立ち上がり校章を制作していくシーンは素晴らしい。地元の多くの人に支えられ身守られて開校した海津小学校の子どもたちのいきいきとした表情をカメラは丁寧に見つめる。「海津の子」が希望に他ならないことが素直に伝わってくる。新設された「地域未来デザイン賞」という言葉がしっくり来る地域の今後の可能性を強く感じさせる良質な番組。
審査員 藤森 研 氏
ともすれば回顧ものになりそうな5つの小学校の統廃合を、「新しい1つの小学校の門出」と前向きにとらえた教育関係者、番組制作者の視点が素晴らしい。外からの目で「過疎化」と呼ばれる現状を、視点を変えて根本から変革していくヒントになる。
新小学校の開校の過程で、民主的、参加型の手法を大胆に取り入れたことにも目を開かされる。
五弁の花の校章は、地元の高校生がデザインし、アンケートで決めた。校歌も、児童たちから「入れてほしいワード」を聞いて、地元出身の若い女性シンガーソングライターが作詞作曲している。
彼女が言う子どもたちの「超キラキラしている」群像が、まぶしい。他の地にも大いに参考になりそうな優れた作品である。
審査員 日笠昭彦 氏
閉校を追った企画は時々見ますが、この企画が際立っていたのは制作者の視点です。五つの学校の存在を桜の花びらに表現した新しい校章は高校の美術部の生徒たちがデザインしました。そこに込められた思いがまずいい!新しい校歌を口ずさむ子どもたちの表情も地域に力を与えてくれるはずです。回顧録に終わりがちな閉校・統合という出来事を「自分たちの手で新しい学校を船出させよう」という前向きなアクションとしてとらえ表現しました。悲しくない!皆さんいい笑顔でした。過疎化や少子高齢化が深刻な事態を迎えている他の地域でも、この企画は参考になるのではないでしょうか。一点注文を付けるなら、タイトルは記憶に残りませんでした。
審査員 服部洋之 氏
まさしく「地域未来デザイン」である。ケーブ局は、もはやインフラ産業でもコンテンツメーカーでもない。「地域課題解決事業」であり、この活動により最適なまちづくりを促し域内消費を実現させ、ひとを創る。「縮小」なのではなく「縮充」なのだ。番組は、閉校合併というベクトルを「開校」に変え、地域と共に次のステップへ進んでいく提案をした。いわば新たなコミュニティをつくる仕事の中に、ケーブル局の未来があると感じる。
審査員 金森郁東 氏
新たに開校した海津小学校を切り口に制作された番組。
とにかくポジティブな取り組みにとても好感がもてました。制作側が前向きで地域を愛していることが映像から伝わってきます。その背景には長年続いていた各校の廃校後統合されたる経緯がありとても後ろ向きな、側面がありますが映像からはとにかく前を向くと言う地域の方々の取り組みを優しく切り取り作品をまとめています。
とても幸せな気分で全編を拝見出来ました。地域未来デザイン賞にふさわしい作品です。
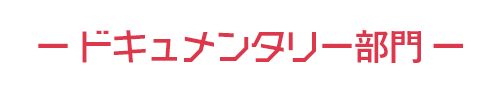
優秀賞
NHK WORLD-JAPAN賞
株式会社インフォメーション・
ネットワーク・コミュニティ
小田切の野菜はおいしいんです
~過疎と高齢化 農業の明日~
受賞者の声

太田 朝子 さん
審査員長 音 好宏 氏
農業の担い手の減少・高齢化、耕作放棄地問題など、長野市・小田切地区の農業が抱える問題と、それらの難問に向きあいながらも、この地域の農業改善に取り組もうとする酒井昌之さんの姿を通して、日本の農業の実相と他エリアのも共通する課題を浮き彫りにする。長期取材を続けてきたからこそ、酒井さんの農業に対する熱い思いとその苦悩が、映像から沁み出てくる作品。
審査員 橋本佳子 氏
今年度にノミネートされたドキュメンタリーのなかで個人的にはベストな番組。一人の高齢男性が農業と向き合う姿と日本の中山間地域の課題を重ね合わせて 6年にわたり記録した。耕作放棄地を耕し続ける酒井さんの姿は誇りに満ちている。酒井さん越しの取材で見えてくる小田切の農業は、このままでは衰退していく日本各地の農業そのものが抱える問題でもある。その厳しい現実と遠からず人生に幕を閉じようとしている酒井さんの姿が番組で交錯して胸をつかれる。アマワラビ、林檎、どの作物のシーンもそれぞれに愛おしく描かれ心に残る。
審査員 日笠昭彦 氏
「畑が森林化した…」そんなショッキングな映像から始まる作品。やがて中山間地の農業の、あるいは過疎高齢化のリアルな姿を目撃することになります。その取り組みは尊いけれど81歳に背負わせるにはあまりにも事態は深刻だと思い知らされます。ところでこの作品は音の使い方も巧みです。ナレーションとインタビューが多くの面積を占める番組が多いのに対し、酒井さんと市民農園の利用者、地元の買い物客とのやり取り、野焼きや子どもの歓声など、現場で拾った生の音が小田切の空気を伝えてくれています。冬景色と夏景色を背景に音声通話で酒井さんの闘病を描写する手法も見事でした。様々なことを考えさせられる奥行きのある企画です。
審査員特別賞
山口ケーブルビジョン株式会社
ソメイヨシノを救え
さくらの守人 ふたたび
受賞者の声

香川 延彦 さん
審査員長 音 好宏 氏
ソメイヨシノをてんぐ巣病から守る「さくらの守人」活動を始めた水津浩・久美子さん夫妻の活動を改めて振り返るとともに、山口大学・佐々木一紀助教、防府高校佐波分校さくらの守人さくら班など、この活動に共鳴する人たちが増え、広がっていく様子が丁寧に描かれている。3年半にわたる長期取材ゆえ、淡々とした展開ながらも、説得力のあるレポートとなっている。
審査員 橋本佳子 氏
根気よく桜を守る水津さん夫婦の4年近い日々を記録した佳作。二人だけでスタートしたソメイヨシノを病気から守る活動、その小さな力が次第に大きく様々な形で広がっていくプロセスが見事に捉えられていることは特筆に値する。スタッフが、長期に丁寧に取材を重ねた賜物と思う。日本の多くの街で見てほしい番組。一点だけ個人的に少し違うかなあと感じたのは音楽の使い方。全編ほぼどのシーンにも音楽が載せてあり番組全体がのっぺりしてメリハリがなくなりとても勿体無いと思った。
審査員 藤森 研 氏
山口市徳地の水津夫妻による活動を、伴走するように記録し続けた「ふたたび」の作品。何年にもまたがる映像のため、3人娘が成長していくのが可愛い。
今回は「染井吉野」の名の由来から始め、その天敵ともいうべき「てんぐ巣病」をテーマに据えた。予防ができず、患部を伐るのが治療法。防府高校佐波分校生が手伝い、伐採した木をランプに加工する班もできている。他の作品でもそうだが、高校生たちが活発に活動する映像には、いつも元気づけられる。
山口大での「てんぐ巣病」研究も少しずつ進み、他の地域との交流も広がる。日本の桜の約8割がソメイヨシノだそうだから、一地域の取り組みの報告は全国的な意味も持っている。
奨励賞
株式会社ジェイコム埼玉・東日本
東上・川越局
脚折雨乞 ~人々をつなぐ龍神~
受賞者の声

中井 尚也 さん
審査員 橋本佳子 氏
コロナ禍を経て8年ぶりに開催された伝統的な迫力ある祭の貴重な記録。祭本番までのプロセスを丁寧に取材していくことで、時代とともに祭の形は変容しても、コミュニティにとって不可決な行事であることが随所から伝わってくる。日本の各地と同様、ここでも高齢化などで祭の存続が厳しい。でもなんとか伝統を引き継ぐという人々の想いが強く感じ取れた。なにより、祭に参加している人々の表情が素晴らしい。どのシーンも人々の表情がきわだち、そのことが祭の映像を臨場感あふれるものにしている。
審査員 藤森 研 氏
麦藁と竹で3トンもの巨大な龍を9か月前から作る。当日は300人が担ぎ、2万人が見る。首都圏にこんなに大規模な行事が残っているのかと驚く。
保存会の新会長や、「総指揮」の副会長らの間の人間臭いやりとりも遠慮なく録音しており、予定調和ではないリアルな息遣いが伝わる面白い作品だ。壮大な行事も、一人ひとりの人間に還元するとこうなるよね、とうなずかされる。
当日の「練り」では、パキパキという音とともに竹が折れて、龍の口が曲がってしまうハプニング。急きょの修復作業も臨場感があり、観る者を逆に引きつける。
だが何といっても最後の場面がいい。誰もいなくなった翌日、池の水面にひっそりと、乞うた通りに雨が降る。とてもよく構成された傑作だ。
審査員 金森郁東 氏
「すねおりあまごい」と言う巨大な龍神を作り練り歩く奇祭です。
全国どの地域にも当てはまるが人口減少により祭事の存続は共通の悩みだと思います。
その背景を、丁寧に切り取り前を向くと言う作品で取材の丁寧さも際立ち、竜神様解体後に藁を大事そうに持ち帰る方の表情が良いですね。
しかし、近年農業の機械化による藁不足も悩みの種ですね。その翌日雨が降ると言う落ちに幸せを感じます。
4年に一度と言う貴重な体験を地位の方々と共有している制作局の取り組みも好感が持てます。
奨励賞
株式会社日本ネットワークサービス
掌のアイデンティティ
~時代を生き抜くハンコ屋の挑戦~
受賞者の声

松村 涼平 さん
審査員 日笠昭彦 氏
地場産業の今昔を紐解きながら、その土地と人を見つめる好企画です。冒頭から情報満載!ハンコの多様な姿を知りました。人への密着というよくある手法ですが撮影・編集が的確なのでストレスなく見られます。一点、知事との面談シーンで「(ハンコで)ワインのエチケットのプライベートトラベルが~」という発言が意味不明のまま迷子になりました。「ワイン王国の視聴者なので地元の人は分かる」ということなら問題ありませんが、県外でも見せる番組なら解説が必要です。また演出面ではタイトルのロゴ、たとえば「掌」や「挑」などの文字は押印っぽい入れ方で工夫する手もありました。地場産業の振興に四苦八苦する人たちに勇気を与える番組です。
審査員 服部洋之 氏
市川三郷町六郷地区は日本一のハンコの町だが多くの課題を抱えている。公的な書類から印章が不要になっていき“ハンコ”が日常から消えつつある。事業継続も危ぶまれる中、ハンコを工芸やアートに昇華させて新しい価値に転換させた原田さん。発想と行動力が地域に前向きな力をもたらす。原田さんの想いを生かしながら、苦悩するハンコ産業の知られざる側面をあぶりだす。ハンコに関する、今現在の「知」を享受できる番組である。
奨励賞
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社
令和6年度伊萬里神社御神幸祭
~祭りでつながり 祭りをつなぐ~
受賞者の声

綾部 亜侑美 さん
審査員 日笠昭彦 氏
生音だけで20秒近く…その後「トンテントン祭り」の言葉を受けて軽快な音楽がフェードイン…そんな手慣れた導入で臨場感を演出していました。「伝承と団結」というテーマが明確で、練習や神輿の修復、祭りの功労者の死去など過不足なく描写。中でも祭りの伝承のために中高生の参加を認める合戦規定と、それに対する(合戦死亡事故の遺族らで作る)市民の会の申し入れをどう扱うかは難しい判断だったと思います。市民の多くが楽しみにしている祭りを客観視して、安全対策を分かりやすく表現した点は評価できます。ただ、実行委員長の「去年参加した中学生は皆楽しかったと言っている」のひと言は、扱いに疑問が残ります。ぜひ議論してみてください。
審査員 金森郁東 氏
全国的に祭りに危険はつきもので私、他地域でも私の目の前でけが人が出て祭りがその場で即刻中止になる等、経験してきてやむを得ないではなく、どうしたら安全開催が出来るかを切り口にした番組です。
うまくまとめているがナレーションによるところが大きいので、その分祭りの臨場感が減り映像の迫力が少し希薄になるのが残念です。祭りのハイライト部分だけでも臨場感のある音声にして頂けるとずいぶん良くなるかと思います。
奨励賞
株式会社ジェイコム九州 熊本局
What is “HINAN”?
~外国人と防災
熊本地震からの教え~
受賞者の声

山口 大祐 さん
審査員 服部洋之 氏
「企画の目線」が大変興味深い番組である。真の意味でインクルーシブ(包摂的)な視点がこの番組にある。この地域には多くの外国人労働者がいるため、多言語での防災マップや案内は充実していた。しかし、である。実際の災害時において、日本語の「話し言葉」と「書き言葉」の曖昧さに課題があった。日本語が聞き取れても「鉄道は不通」を「普通」と解釈してしまう。細かな課題と気づきを丁寧に解き明かす工夫が包摂性を高める。
審査員 金森郁東 氏
What is “HINAN”?今回、防災をテーマにした作品が多い中、なるほど、目線を変えればこれだけたくさんの問題をかかえているのかが私事のように感じた内容でした。
外国人にとっては難しい日本語と意思疎通を切り抜いていて、“電車は普通です”が意味不明など平時では何度か行き来して解消できることが不可能な状況であることを伝えてくれている。能登半島地震のことも事例として言及してくれていてとても参考になりました。
奨励賞
大分ケーブルテレコム株式会社
~赤瀬川原平 没後10年 特別番組~
「赤瀬川が大分に残した軌跡」
受賞者の声

利光 健 さん
審査員 橋本佳子 氏
前衛芸術家 赤瀬川原平そして作家 尾辻克彦。マルチに活躍し、多彩な顔をもつ世界的な表現者を新たな視点で読み解いた。キーワードは地元「大分」だ。4歳から高校生になるまで暮らした大分という街と人々を掘り起こし、赤瀬川の原点ともいえるいわば「青の時代」にフォーカスした着想が新鮮だ。新世界、ネオダダ、雪野氏、赤瀬川のルーツを丹念に探りつつ、地元の街にそれを継ぐものを発見していく。没後10年にふさわしい見応えのある番組だった。
審査員 藤森 研 氏
知っているようで知らなかった赤瀬川原平の素顔と業績を、大分で肩をこらせずに辿り、「彼は一体何者だったか」に迫っていくユニークな作品だ。
親友だった雪野さん(89)の回想が楽しい。別れ際に「サイナラ」を延々と言い合い赤瀬川のしつこさに負けたという「サイナラ合戦」の話は笑える。
古びた壁に残るドアの痕跡も赤瀬川は芸術と位置づけ、期待外れだった助っ人野球選手の名を取り、それらを「トマソン」と名付けた。今も大分の芸術短大生らが、路上でトマソン探しをしている。
大分の清掃運動のグループは、赤瀬川に倣い人目につくようにトイレ清掃に励む。元々は外見を取り繕う前回の東京五輪への皮肉のメッセージだった。
「無意味な面白さ」と雪野さん。「やっぱり芸術家なんだと思いますよ」。赤瀬川のユーモアをたっぷりたたえた「反芸術」「反社会」は、何やら懐かしい。
新人優秀賞
株式会社あいコムこうか
湖南馬事センターの半年
~目指せ!一流のホースマン~
受賞者の声

久保田 圭介 さん
審査員長 音 好宏 氏
滋賀・甲賀市にある湖南馬事センターで、競走馬育成騎乗者を目指してトレーニングを積む研修生たちに半年間密着して、その成長を追いかけるというテーマ設定が、まずユニークである。ほとんど競走馬に触れた経験のなかった新入研修生たちが、だんだん馬に慣れていく様子が映像から伝わる。ナレーション過多で、やや説明的な部分が気になるものの、研修生たちの人間味をよく拾い上げていて、好感の持てる作品。
審査員 橋本佳子 氏
競走馬の世界に魅せられ馬事センターに集まった若者たちの半年にわたる喜怒哀楽を追った存在感のある青春ドキュメンタリーとして番組に仕上がっている。あまり知られていないホースマンの世界を見事に表現した。企画の目のつけどころ、取材対象へのアプローチ、絞り込み方、伝えるべきことの取捨選択、長期取材のまとめ方、どれもが新人の域を超えて素晴らしい。もし欲をいえば、もう少しだけ授業の内容にこだわるところがあっても良かったかもと感じた。
審査員 日笠昭彦 氏
いい舞台設定でいい人選です。3人の最後のコメントを聞いて「何かをつかんだ時、人は自分の言葉で語ることができるんだなぁ」と実感しました。冒頭とラストの「三乗七厩」もいいアクセントになっていて、細部までこだわった構成です。今後の期待を込めてアドバイスするなら、タイトルに掲げている「半年」は、内容によってはもう少し刻んでも良かった気がします。たとえば騎乗訓練は「騎乗訓練○○日目」という目印があると、一層理解が進みます。また後半では、振り返りの手記がそれぞれの内面を知るのに効果をあげていますが、これについてはもう少し見せ方を工夫できると良かったですね。新人賞の枠に収まらない作品です。今後が楽しみです。
新人奨励賞
株式会社倉敷ケーブルテレビ
歌い継げ!下津井節
~風待ちの港に吹く新風~
受賞者の声

土岐 和也 さん
審査員 藤森 研 氏
民謡(音)と、瀬戸内の風景(映像)との、心地よいアンサンブル(合奏)とも言いたくなる穏やかな秀作だ。個人的な話だが評者は閑谷学校や鞆の浦へ行って瀬戸内の風土のファンになったばかりなので、味わいはひとしおだった。
番組では、民謡のプロが歌う確かな下津井節が終始背景に流れて、安心して見ていられる。
「100年後に残す、ほんの第一歩」と民謡歌手、津本ゆかりさんの意気込みは頼もしい。「さざなみ会」の祖母から孫娘への踊りの継承も具体的に描かれている。
本当に、この作品が100年後に、貴重な映像記録として再上映されるような気がする。
審査員 服部洋之 氏
少子高齢化のもと、伝統文化の継承は大きな課題である。下津井節全国大会の優勝者である民謡歌手、津本さんの想いから始めた「宵灯り」。催しに向かって、様々な方向から地域の人々を巻き込んでいく奮闘ぶり。唄と踊りは万人が楽しめる。踊りの伝承者と中学生が世代を超えて、想いでつながっていく。参加する事へのインクルージョン、自分事化していくことで、前向きに継承できる地域活性にむけた仕組みのお手本がここにある。

優秀賞
伊賀上野ケーブルテレビ
次世代に残したい伊賀弁
受賞者の声

向井 大介 さん
審査員長 音 好宏 氏
関西弁とも、他の三重県のエリアの方言とも異なり、伊賀地域だけで使われている伊賀弁を、クイズ形式で紹介していくことで、伊賀弁の特性、エリア性を、参加・視聴する地域の人とともに確認していける作りとなっている。県域放送ではなく、伊賀上野地域をエリアとするケーブルテレビならではの作品。全体として展開もテンポよく、見やすい構成であるところも好感が持てた。
審査員 服部洋之 氏
伊賀上野は地理的特異性がある。天気予報、東海地方か近畿地方か?NHKは大阪、名古屋の両方が受信できる?名古屋方面への通勤需要も多いがJRは西日本。こうした地域性が伊賀弁に表れている。番組では、老若男女の聞き取り調査を軸に、伊賀の歴史的、地理的な成り立ちを挟みながら「伊賀ことば」の特異性をあぶりだしていく。「無理に残す必要はないが、日常の人との思い出で」というメッセージに伊賀コミュニティを感じる。
審査員 金森郁東 氏
コミュニティ部門の優秀賞にふさわしい作品です。
伊賀弁をテーマに制作されていて新春特番として制作されたようだが、うまくとらえられていて好感が持てます。取材も丁寧で素敵です。私は能登生まれですが似たような言葉もたくさんありつつ、まったく違う表現もありとても面白いです。
このつくりは他地域でも通じるものがありフォーマット化して各地でシリーズ化するのも面白いと感じました。
奨励賞
株式会社ジェイコム千葉 東葛・葛飾局
株式会社ジェイコム千葉 東関東局
株式会社ジェイコム千葉
第76回東葛飾地方中学校
駅伝競走大会
受賞者の声

髙田 裕一 さん
審査員 橋本佳子 氏
3時間超えの完全版が見たくなる!短縮版30分での審査ではあったが画面から、一瞬も目を離せなかった。75の中学校が競う歴史ある32キロの駅伝。10人の生徒がつなぐ襷をめぐるドラマを、完全生中継するという快挙に盛大な拍手を送りたい。各地点での中継も要所のポイントをきちんとおさえ、綿密な事前取材に基づいた解説も的確で楽しめた。地元の人々はこんな素敵な中継を視聴でき幸せだ。ここから全国大会へ向けて一層の声援を送りたくなる。毎年の恒例番組に是非なって欲しい。
審査員 服部洋之 氏
かつて駅伝中継は地上波局のお家芸といわれ、マイクロ伝送、SNGや移動中継機材など大きな資本が必要だった。近年、Wi-Fi伝送やスマホ撮影等の簡便なシステムが普及したため可能になったといえる。一方“スポーツ中継は結果がわからない、故に生中継でプロセスを共感してほしい”そんな制作者の熱意が強く感じられたのも事実である。実況もスイッチングもカメラワークも、スタッフ皆がその想いのもと実現させた番組といえる。
奨励賞
株式会社TOKAIケーブルネットワーク
地域ド密着農業バラエティ
いけや賢二のイケいけファーム!
受賞者の声

左・望月 隆宏 さん(制作者)
中央・池谷 賢二 さん(出演者)
右・和泉 由希子 さん(出演者)
審査員 日笠昭彦 氏
「農業芸人×プロ雀士×素人(&寅さん)」という座組が興味深く、中盤まで面白く見られました。特に和泉さんの立ち位置(冷めたツッコミ)が良く今後も大事なポジションになりそうです。演出面で気になったのは、道の駅にネギを置いてもらう場面やコメをふるさと納税の返礼品にしてもらう場面で、全く障害が無く交渉になっていない点。例えばここで、交渉成立に向けて課題など提示されれば次の展開にもっと緊張感を与えられたのでは?また、冒頭で「お金!お金!」と連呼する割にエンディングまで経費や値付けに触れていないのも気になりました。バラエティと位置づけるなら、もう少し演出上の“山と谷”を作る仕掛けが必要かと思います。
審査員 金森郁東 氏
この作品もコミュニティ部門にふさわしい秀作です。芸人さんを使い、いろいろなミッションをこなして行く様は、テンポもあり初見でも入りやすいです。
制作陣のカメラでどこか雑駁な感じもするけど、それが良いところでもあるので今後にも生かして頂きたいです。4K制作との事でその観点からも拝見しましたが、機材メリットを活かし撮影されているなと感じました。
今後は大画面で見ても座りの良い画作りにも取り組んで頂けると良いですね。
奨励賞
株式会社CAC
わたしのストーリー
~あなたのエピソードを映像化~

※この番組は配信できません
受賞者の声

平賀 華恵 さん
審査員長 音 好宏 氏
タイトルにあるように、「あなたのエピソードを映像化」するという設定で、このエリアの視聴者の地域にまつわるエピソードを、ショート・ドラマにしてしまうという挑戦的な作品。素人のドラマ出演という難しさもあるが、地元住民が「参加するテレビ」というコンセプトは、ユニークでもある。
審査員 藤森 研 氏
地元の人の出来事を、地元の素人がドラマとして演じる新機軸の試み。「何気ない毎日も、振り返れば物語」という発想がいい。
3本立てで、1本目は「配達は、品物だけでなく元気も運ぶ」。2本目は「少子化対策として結婚式を憧れに」と、野道の花嫁行列を実行する人の話。3本目は「イルミネーション・ツリーで地域を一つに」。いずれも、わかりやすいプロットだ。
感動的なドラマとまでは行かないが、顔見知りの人が演じるコミチャンらしい作品。観る方も「あ、だれちゃんだ」と話しながら、楽しいだろうなと思う。
奨励賞
山口ケーブルビジョン株式会社
こんなコッペパンを作りたい!
~防府商工生の試み~
受賞者の声

香川 延彦 さん
審査員 日笠昭彦 氏
地元の課題解決に取り組む「総合実践」の授業はCATVの立ち位置とも親和性が高い企画です。商品開発はもちろん動画撮影・巻紙制作など活動は多岐にわたりますが、冒頭から番組はテンポ良く情報もよく整理されていました。長期取材は大変だったと思いますが、時折挟む写真構成も物足りなさは感じずかえって効果的でした。郡司先生のインタビューや16分付近の地元スーパーへのお願いはもう少し短くして、その分の尺を奮闘する生徒同士のやり取りなどに使えたら深みが増したと思います。さらに欲を言えば購入者のインタビューは店頭だけでなく、帰宅後(食後)の感想をLINE等でいいので盛り込みたかった。「頑張るぞ!オー!!」はCATV側の演出だとしたら不要です。
審査員 金森郁東 氏
この作品もコミュニティ部門にふさわしい秀作です。
とにかく全編、制作陣の温かみと映像愛が伝わってきます。やはり取り組みには取材対象との関係値構築が一番良い結果をつくると言う模範例だと思います。
最初はこの商品ずいぶん豪華なコッペパンのパッケージで高額だと思いましたが、見進めるにつけパッケージの巻紙に仕込まれたQRコードと言い、生産者と直結する仕組みとかとても良いですね。とにかく拝見して幸せになる作品でした。
新人優秀賞
KCVコミュニケーションズ株式会社
ひたすら! 幸せのおすそわけ
~ふたつの国を繋ぐ 日田の布屋~

※この番組は配信できません
受賞者の声

末松 智宏 さん
審査員長 音 好宏 氏
ナイジェリアからアフリカ布を輸入・販売を続けてきた小関はつみさんの活動にフォーカスして、小関さんの周りで行われてきた等身大の文化交流のエピソードを紹介。展開にやや説明的なところもあるが、紹介されるエピソードは、心温まるものばかり。地域再発見の物語集としても評価したい。
審査員 橋本佳子 氏
SNSが普及してはや20年。その陰の部分が最近は目立つが、この番組はSNSがうんだ奇跡のような出来事に焦点をあてたショートエッセイともいえる。オープニングの日田の導入が良い。インタビューがメインの構成素材だが、それらを駆使して、日田とアフリカという空間と60年前の歴史という時間を見事に超えて見せた力量は、新人とは思えず舌を巻いた。ともあれ、「おすそわけ」から広がる世界を堪能させていただき、心もちょっぴり明るくなった。
審査員 藤森 研 氏
主婦がSNSで偶然に知り合ったナイジェリア人。竹箸をおすそわけしたら、9か月後、お礼にアフリカ布が送られてきた。懐かしさを感じて調べてみたら、日本が以前、経済援助で絞り模様を伝えていたのだった。やがて主婦はSNSでアフリカ布を販売し、展示会やコンサートを開くに至る。稀有な物語だが、実話だ。
主婦の眼力、熱意には頭が下がるが、それを見つけて作品にまとめた新人制作者も、お手柄だ。
日本はかつてODA大国だったが、こうして役に立っていたことを改めて考えさせられる。国際協力を「おすそわけ」でとらえた、気持ちのよい作品だ。
新人奨励賞
株式会社倉敷ケーブルテレビ
音のない世界と、
音のある世界をつなぐ
~倉敷市地域おこし協力隊
難聴のライター~
受賞者の声

小玉 優 さん
審査員 日笠昭彦 氏
好企画です!好きなことを仕事にすることは簡単ではありませんが難聴の女性が果敢にそこへ挑む物語。主人公はインタビュアーとしても優秀です。これは全国の制作者に参考にして欲しいことですが、高石さんは取材の最後に「私からは大体聞けたと思うんですけど話し足りないことはないですか?」と相手に問いかけます。真摯で丁寧な仕事ぶりが伺えます。演出面で気になったのは、せっかくスタジオのリードを手話で伝えたのなら受けも手話で通して欲しかった。またサイドスーパーやネームスーパーは読みやすい反面、院内学級の子供達の作品がつぶれてしまい残念でした。ベースは無しかハーフ=透過で、文字数ももう少し減らした方がいい気がします。
審査員 服部洋之 氏
ニュース特集枠という短い時間の中で、高石さんの難聴ライターとしての活動や視点を通して様々なメッセージが込められている。社会における障がい者の見方や見られ方、彼女の言葉である「しょうがないと割り切る」気持ちにさせる包摂性の無さ、地域おこし協力隊を通して挑戦を広げた高石さん自身の想い、高石さんだからこそ見える課題を丁寧に盛り込んでいる。協力隊卒業後、彼女が倉敷に何を投げかけるのかが楽しみである。
4K特別賞
JCOM株式会社
株式会社ジェイコム湘南・神奈川
湘南・鎌倉局
キナミのパン日和

※この番組は配信できません
受賞者の声

大森 未侑 さん
審査員 藤森 研 氏
風を感じさせるカメラ・ワーク。あっさりした女優、木南晴夏のイメージともマッチする。早春の上天気。
何が起こるわけでもなく、町をそぞろ歩いてパンを賞味するだけだが、チャンネルを合わせていると何やら爽やかな気分になってくる、コミチャンらしい小品だ。横須賀、段葛、森戸大明神と、湘南の春景色も楽しめる。
「サクサクと歯切れがいい」「クロワッサン軽い。バターしみっしみなのに」と木南のレポートは巧まない。力まずサラッと、春の空気とパンの情報を届けようとする制作姿勢に、好感が持てる。
審査員 服部洋之 氏
4Kコンテンツは“ならでは”か“でなくとも”に分類される事が多いが、この番組はちょうど中間にある。パンだけに特化し、パン愛溢れる店主とのニッチな会話、キャスティング✕店✕人(店主)の相乗効果で興味を引くコンセプトが際立つ。4Kの特徴を生かし、パン艶や生地のシズル感を美味しく引き出す撮影編集に拘った。シズルは人の脳を刺激し、映像では伝えきれない「味と香り」を想像させるのに一役買ったといえる番組だ。
審査員 金森郁東 氏
立場上、4K制作と記述があるものは別で全作見るようにしています。
見進めていくなかで今年は該当作無しとなるかもと思いながら最後にこの番組に巡り合いました。
構成上、荒っぽくHDで制作すると地上波バラエティーのコーナーになりかねないのですが4K制作の醍醐味を教科書通りに制作されています。特に好感がもてるのは物撮りの丁寧さ被写界深度を活かした映像作り、テロップのまとめの良さ等、4Kの利点をフルに活用しています。
制作されたプロダクション様に敬意を表します。
審査員
写真をクリックするとプロフィールをご覧いただけます。
お問い合わせ
【一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 コンテンツ&HR推進部
】
〒104-0031 東京都中央区京橋1-12-5 京橋YSビル4F
tel:03-3566-8200 fax:03-3566-8201
jcta_contents-lab@catv-jcta.jp
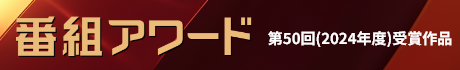
















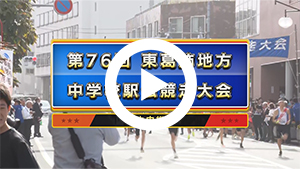


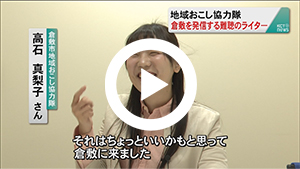
 審査員長
審査員長 審査員
審査員 審査員
審査員 審査員
審査員 審査員
審査員 審査員
審査員